- 年収は103万にするのと130万にするのどっちが得?【2022年度版】
- 103万円の壁にこだわる人は損をするって本当?
- 103万超えたらいくら払うことになる?




親や配偶者の扶養内で働く場合、いくつかの年収の壁に注意する必要があります。
その中でも「103万円の壁」と「130万円の壁」については聞いたことがある人も多いかもしれません。
税制上の扶養や社会保険上の扶養に関わる金額のため、扶養者の控除額にも影響が出てきます。
働き損を避けるためには、こうした壁についてしっかり理解しておく必要があります。
では103万円の壁と130万円の壁にはどういった違いがあるのでしょうか。
103万と130万どっちが得か考える前に知っておきたいこと【2022年】
103万の壁や130万の壁は扶養控除に大きく関わってきます。
では、そもそも扶養控除というのはどのような制度なのでしょうか。
パート妻にとってどちらが得か考える前に、まずは扶養控除についての正しい知識を身につけましょう。
130万の壁に関係する社会保険上の扶養控除
扶養とは、家族の生計を主に担っている扶養者が、配偶者や子ども、親など収入が少ない家族を経済的に支えることをいいます。
社会保険上の扶養とは、扶養されている人が扶養者の社会保険(健康保険・厚生年金)に入ることです。
そのため、扶養されている被扶養者は自分で社会保険料を納める必要がなくなります。
ただしこの制度は、被扶養者の年収が130万円未満、なおかつ扶養者の収入の半分未満であるのみ認められています。
被扶養者が60歳以上の場合は年収の上限が180万円未満となります。
103万の壁に関係する税制上の扶養控除
税制上の扶養とは、家計を支える納税者の配偶者や子どもの年間給与収入が103万円以下のときに、納税者の所得から一定の金額を控除できる制度です。
しかし、被扶養者の給与収入が年103万円を超えてしまうと、扶養から外れてしまうため、被扶養者も自分で税金を納めなければならなくなります。
子どもや親は扶養控除、配偶者は配偶者控除の対象として、納税者の負担が軽減されます。
パート妻が知っておきたい103万円の壁とは
パート妻の年収が103万円を超えてしまうと所得税が発生して、税制上の扶養から外れてしまいます。
そのため、これを「103万円の壁」と呼んでいます。
年収103万円を超えると所得税がかかる
所得税は、その年1~12月の収入が103万円を超えると、かかるようになります。
なぜ103万円かというと、給与所得控除55万円と基礎控除48万円を合わせた金額が103万円だからです。
つまり103万円までの年収ならば、控除額の範囲に収まるため、所得税はかかりません。
これを超えてしまうと、103万円を超えた分に対して所得税が課税されます。
この場合、非課税分の交通費は年収に含まれません。
年収103万円以内ならば税金の負担を軽減できる
年収103万円を超えると、扶養控除が受けられなくなります。
その結果、扶養している親や配偶者の税金が上がります。
たとえば、被扶養者が16歳以上で年収が103万円以下の場合、扶養者は少なくても38万円の扶養控除が受けられます。
被扶養者が19歳以上22歳以下ならば特定扶養親族に相当するため、扶養者は63万円の控除が受けられます。
さらに配偶者を扶養に入れる場合は、配偶者控除が適用されます。
扶養者の年収が1,000万円以下で、扶養に入る配偶者の年収が103万円以下の場合、扶養者は12~48万円の配偶者控除が受けられます。
その他にも年収が103万円を超えても、要件を満たすことで控除が受けられる配偶者特別控除もあります。
これは被扶養者の年収が150万円以内で、扶養者の年収が1,095万円以下であれば満額の38万円の控除が受けられる制度です。
被扶養者の年収が上がると、控除額は段階的に少なくなっていきます。
パート妻が知っておきたい130万円の壁とは
「130万円の壁」とは、社会保険の加入義務が発生する年収額です。
被扶養者の年収が130万円以上になると、扶養から外れてしまうため、それまで会社側から支給されていた家族手当などの手当がもらえなくなってしまいます。
年収130万以上になると社会保険の加入義務が
パート妻の年収が130万円以上になると、親や配偶者の社会保険上の扶養から外れてしまいます。
そのため、自分で社会保険に入らなければならず、自分で社会保険料を支払わなければなりません。そのため、社会保険料の分だけ手取りが減ります。
この130万円には交通費なども含まれます。
社会保険には勤務先で加入できるものと、個人で加入するものの2種類があります。
勤務先で加入できるかどうかはいくつかの条件があるため、それを満たせない場合には、国民健康保険・国民年金に自分で加入する必要があります。
年収106万円で社会保険の加入義務が発生することも
たとえ年収130万円未満であっても、以下の5つの要件すべてを満たすと社会保険に入らなければなりません。
ポイント
- 正社員数が101名以上の事業所
- 年収が106万円以上
- 2ヶ月以上継続の雇用見込みがある
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 学生ではない
ココがポイント
正社員数は2021年までは501名以上でしたが、2022年からは101名以上に拡大されました。2024年以降は51名以上まで拡大される予定です。
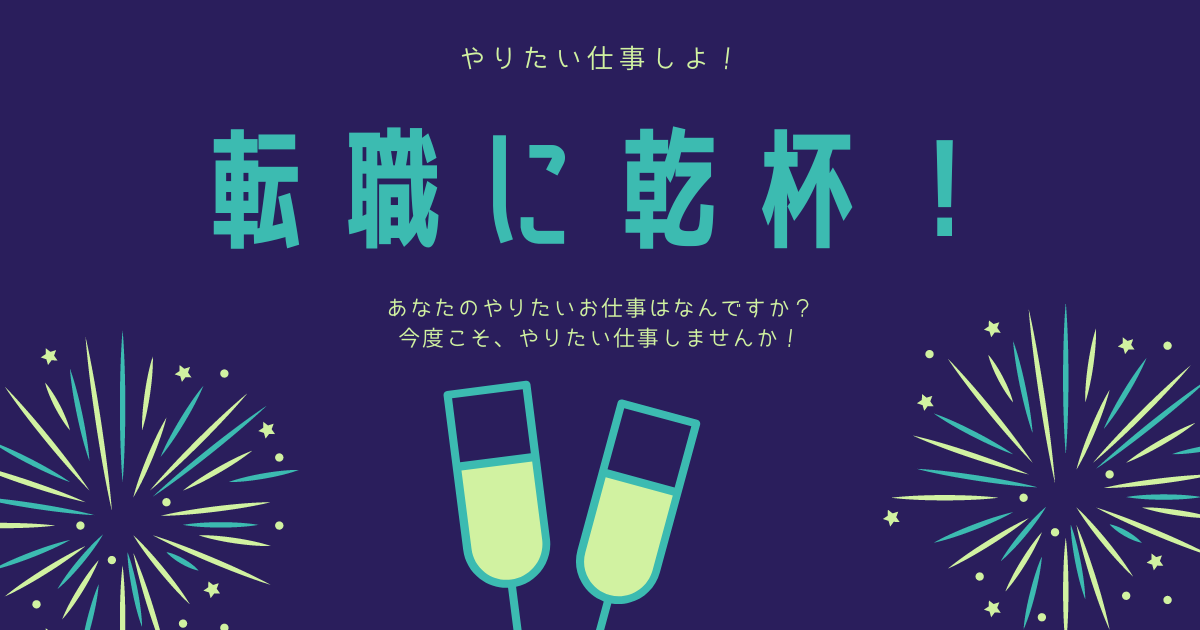
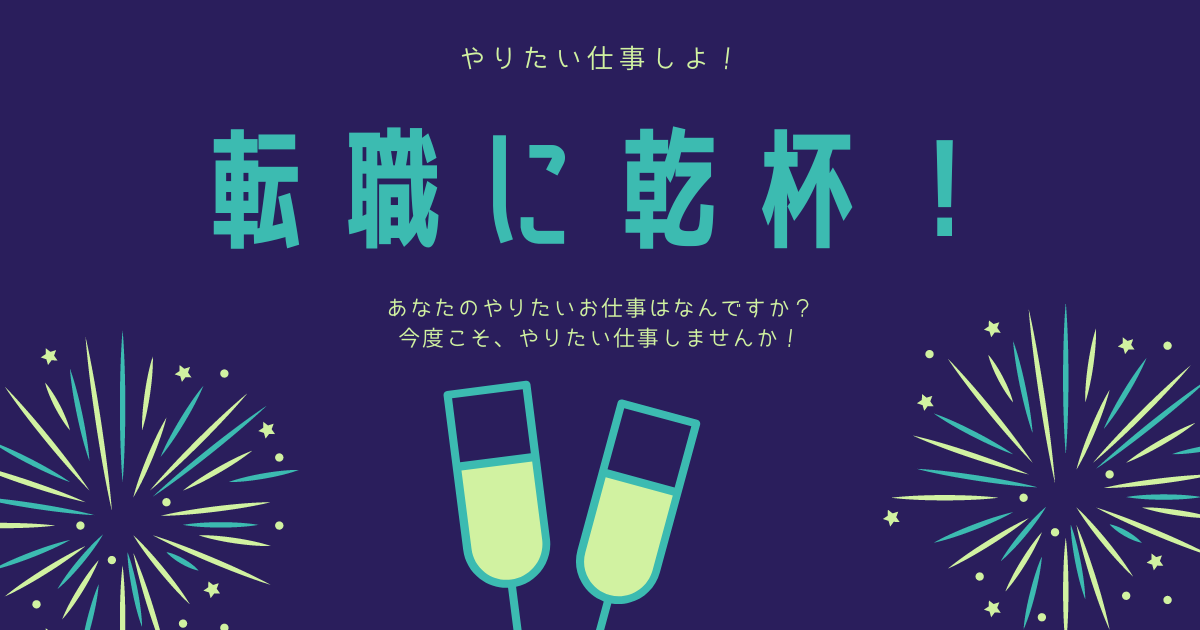
パート妻が年収103万円以下で働くメリット【2024年】
パート妻が年収103万円以下にするメリットは大きく2つあります。
- 所得税がかからない
- 配偶者控除が満額受けられる
103万円以下のメリット①所得税がかからない
所得税は収入から給与所得控除(65万円)と基礎控除(38万円)を引いた課税所得金額を元に算出されます。
つまり65万円+38万円である103万円までは課税所得金額がゼロになるため、所得税がかかりません。
ただし、年収が100万円を超えると住民税がかかります。
住民税は住んでいる自治体や家族の状況によって変わりますが、年収103万円くらいだと、およそ年間1万円かかります。
103万円以下のメリット②配偶者控除が満額受けられる
配偶者控除は、一定以下の所得金額の配偶者がいる納税義務者が受けられる所得控除です。
配偶者を養う行為が税を負担する能力を減らしてしまうという考えから、負担を調整するために設けられています。
年収103万円以下にしておくと、この配偶者控除が満額の38万円受けられます。
103万円の壁にこだわる人は損をすることも
パート妻が年収103万円を超えると、所得税が課税されることから、103万円の壁を意識している人は多いです。
しかし、多少103万円を上回ったとこで大した金額を課税されるわけではないため、そこまで気にしなくても大丈夫です。
たとえば年収104万円に上げたところで、支払うべき所得税は年500円ほどです。
収入が1万円増えて、500円支払うわけですから、世帯収入で考えれば大幅アップなのは間違いありません。
ココがポイント
パート妻が130万円未満まで年収を増やすメリット【2022年】
年収130万円以上になってしまうと、社会保険に加入する必要があるため、手取りが減ってしまいます。
それを避けるためには年収130万円未満に抑える必要があります。
- 世帯収入が増える
- 応募できる求人の幅が広がる
130万円未満のメリット①世帯収入が増える
年収103万円以下と年収130万円未満では、手取りの額に大きな差が出てきます。
130万円未満にしておけば、所得税は支払う必要はありますが、社会保険を支払う必要はないため、世帯収入としてはかなり増えます。
働く時間が増える分、収入も増えるため、家計としてもうれしいポイントです。
130万円未満のメリット②応募できる求人の幅が広がる
年収103万円以下で働くよりも年収130万円未満に増やしたほうが、応募できる求人件数が増えることが多いです。
年収103万円以下に抑えようとすると、月の収入はだいたい85,000円です。
時給1,300円で1日5時間働くとすると、月に13日までしか働けません。
そうなると「週4日以上」が条件になっている求人には応募できなくなってしまいます。
専門職になるにつれて時給は高くなる傾向にあるため、場合によってはさらに日数を減らす必要があります。
ココがポイント
103万円以下で働こうとすると、どうしても選択肢が狭まってしまいます。その分、130万円未満にするとだいぶ幅が広くなります。
パート妻が年収130万円未満まで上げるデメリット【2022年】
ではパートで働いている主婦が年収103万円から130万円まで引き上げるにはどういったデメリットがあるのでしょうか。
- 所得税が発生する
- 働く時間が増える
デメリット①所得税が発生:妻の収入が103万超えたらいくら払う?
パートで働いていて年収が103万円を超えると所得税がかかるようになります。
所得税は課税所得金額をもとに算出します。
たとえば、年収が125万円だと125万ー103万円の22万円が課税対象です。
納める金額はこの22万円に所得税率をかけた値です。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
参考:所得税の税率 | 国税庁
上表から年収125万円だと税率は5%になるため、22万円×0.05で1年間にかかる所得税は11,000円になります。
デメリット②働く時間が増える
同じ時給で給料を上げるならば、その分労働時間を増やす必要があります。
たとえば時給1,300円だとして、年収103万円から130万円未満に上げようとすると1ヶ月あたり約17時間も多く働くことになります。
ココに注意
年収103万円のときよりもだいぶ忙しくなるため、体に負担がかかることも多いです。
パートで働くなら103万円と130万円どっちがお得?【2022年】
それぞれの年収の壁を理解したところで、結局どのくらい稼げば得なのかを解説していきます。
パートで103万円稼いだ場合の手取り
パートナーの扶養に入っている場合でも、年収が103万円だと所得税と社会保険はかかりませんが、住民税がかかります。
配偶者(40歳未満)の年収が500万円だと仮定すると、配偶者控除が所得税に対して38万円、住民税に対しては33万円控除されます。
パートで得た収入と配偶者の手取りを合わせると、だいたい487万円が残ることになります。
パートで129万円稼いだ場合の手取り
収入が129万円だと、所得税と住民税は支払う必要がありますが、社会保険は扶養の範囲内なので支払う必要がありません。
ただし年収103万円を超えているため配偶者控除の対象外となってしまいます。
その代わり、一定の条件を満たせば配偶者特別控除が適用されます。
配偶者の年収が500万円だと仮定すると、配偶者特別控除が適用されて38万円が控除されます。
そうすると世帯全体としてはだいたい523万円が残ることになります。
結論:130万円未満で問題なし!
配偶者の扶養範囲内ならば年収130万円未満ならば、社会保険料を支払う必要がありません。
またパートナーの税金も増えることもないため、103万円のときとそこまで大きな差はありません。
それに対して世帯収入は確実に増えるため、130万円未満を目標にして働いてOKです。
ただし、勤務先によっては106万円から社会保険に加入する必要があります。そうなると大幅に手取りが減ってしまうため、130万円未満だと働き損になる恐れがあります。
ココに注意
社会保険の加入条件についてはよく確認しておきましょう。
主婦の年収が130万超えたらいくら払う?
主婦の年収が130万円を超えてしまうと社会保険料を自分で支払うことになります。
そうすると手取りが大幅に減ってしまいます。
年収130万円の手取り
給与130万円-所得税4,000円-住民税15,500円-社会保険料約19万円
手取り金額:109万500円
年収140万円の手取り
給与140万円-所得税8,500円-住民税24,500円-社会保険料約20万円
手取金額:116万7,000円
年収150万円の手取り
給与150万円-所得税13,500円-住民税33,500円-社会保険料約21万円
手取金額:124万3,000円
年収160万円の手取り
給与160万円-所得税17,500円-住民税42,500円-社会保険料約22万円
手取金額:132万円
年収130万円を超えるなら150万円を目安にする
どうしても年収130万円を超えてしまうようならば、150万円を目安にすると、世帯収入の手取りをそれほど減らさずに済みます。
140万円だと多少働き損になってしまうため、せっかくならばもう少し働いて150万円以上を目指すようにしましょう。
年収130万円を少しだけ超えるのがもっとも働き損になるため、できる限り避けたいところです。
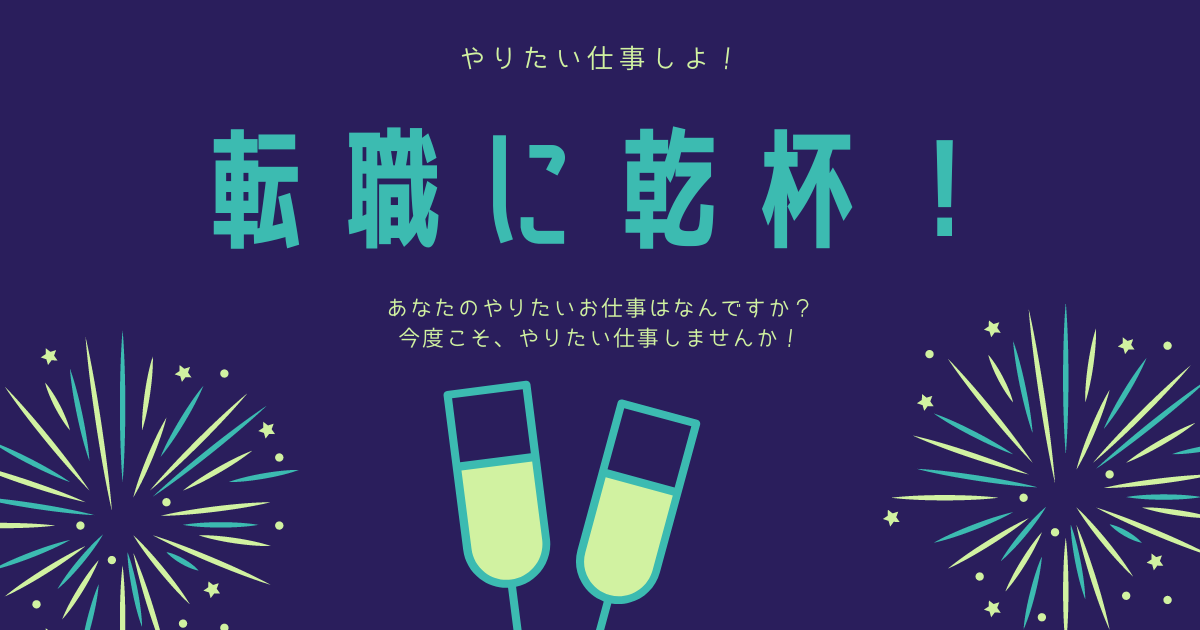
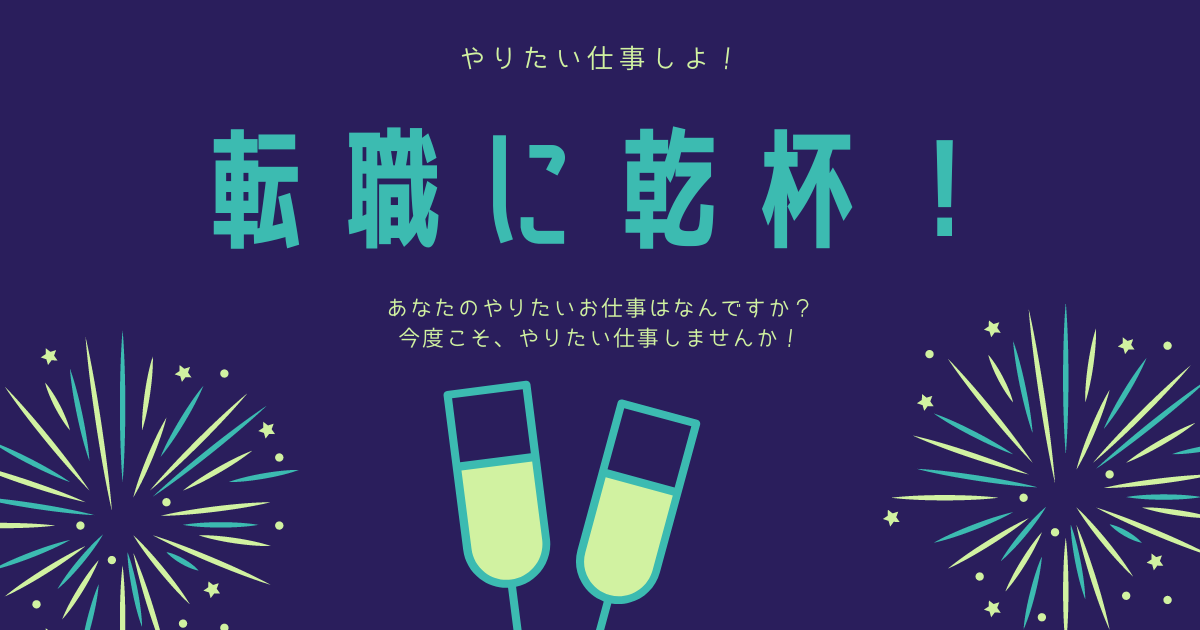
まとめ
103万円の壁と130万円の壁は、言葉だけ見ると同じような意味合いに感じますが、実際内容はだいぶ異なります。
税制上の扶養控除となる103万円の壁は、それほど家計の負担にならないため、そこまで気にする必要はありません。
ただし130万円の壁を超えてしまうと社会保険料を支払う必要があり、だいぶ手取りがへってしまいます。
パートで働くときは130万円の壁を超えてしまわないよう気をつけましょう。
コメント