- 将来なくならない仕事とはどんな仕事?
- 生き残る職業ランキングはどんな感じ?
- これから需要が増える仕事には何がある?




以前まで人間が行ってきた作業はどんどんAIやロボットなどに取って代わられています。
このまま何もしないでただただ今の仕事をしていると、将来的に職を失ってしまう可能性はゼロではありません。
この記事では、これからなくなっていく仕事や生き残る仕事についてまとめています。
将来生き残るために必要なことについてもまとめているため、ぜひ参考にしてください。
これから将来も生き残る仕事・職業
今後AIが発展していけば、人間の仕事を奪う可能性が高いです。
AIは同じような作業を繰り返すことを得意としているため、パターン化している仕事はどんどんなくなっていくでしょう。
逆にパターン化されていない、なかなか予期できないような仕事や想像力が必要な仕事は将来も残っている可能性が高いです。
生き残る仕事・職業ランキング50
今後も生き残るであろう仕事・職業ランキング50を紹介します。
- 1位:精神科医
- 1位:言語聴覚士
- 3位:中学校教員
- 3位:外科医
- 3位:教育カウンセラー
- 3位:バーテンダー
- 3位:助産師
- 3位:ゲームクリエイター
- 3位:旅行会社カウンター係
- 3位:フードコーディネーター
- 11位:小学校教員
- 11位:経営コンサルタント
- 11位:ネイルアーティスト
- 11位:保育士
- 15位:スポーツインストラクター
- 15位:雑誌編集者
- 15位:エコノミスト
- 15位:グラフィックデザイナー
- 15位:観光バスガイド
- 15位:ディスクジョッキー
- 21位:ファッションデザイナー
- 21位:ペンション経営者
- 21位:アロマセラピスト
- 21位:ツアーコンダクター
- 25位:犬訓練士
- 25位:内科医
- 25位:ソムリエ
- 25位:報道カメラマン
- 25位:インテリアコーディネーター
- 30位:映画監督
- 30位:舞台演出家
- 30位:俳優
- 30位:アナウンサー
- 30位:芸能マネージャー
- 35位:コピーライター
- 35位:学芸員
- 35位:声楽家
- 38位:作詞家
- 39位:作曲家
- 39位:料理研究家
- 42位:美容師
- 42位:漫画家
- 42位:手話通訳者
- 42位:社会福祉施設介護職員
- 46位:声優
- 46位:看護師
- 48位:動物園飼育スタッフ
- 49位:ホテル・旅館支配人
- 50位:化粧品訪問販売員
これらの仕事はAI(人工知能)やロボットなどによる代替可能性が少ない職業から将来も生き残るだろうといわれています。
参考:野村総研
将来なくならない仕事:議論が必要な仕事
法律関連で議論が必要な仕事は、AIによって奪われにくいため、将来も生き残る可能性が高いです。
議論を行う場合、これまでのデータや数値に加えて新しい発想力も必要になってきます。
AIは過去の数値などのビッグデータは得意ですが、発想力が必要な数値化できない仕事は得意ではありません。
そのため、人と人との話し合いが必要な仕事は今後AIに奪われることはあまりないと考えられます。
将来なくならない仕事:医療福祉
人と密接に関わるような看護師や医療福祉の仕事もAIに取って代わられる可能性は低いです。
医療の現場では状況変化が激しく、柔軟な対応が要求されます。また予測不能なことが頻繁に起こるため、AIでは対処しきれないでしょう。
また患者のメンタル状況によって対応を変える必要があり、そういった細かい変化にも気づく必要があります。
密にコミュニケーションをとることで成立する仕事のため、今度も生き残る可能性は高いです。
ココがポイント
一部の業務がAIによって効率化されることはあっても、コミュニケーションが必要な業務は将来も残っているはずです。
将来なくならない仕事:クリエイティブな仕事
創造性が必要な仕事はAIに奪われる可能性が低いです。
たとえば、演技などのパフォーマンスは人間がやってこそ感動させられるものです。機械が精密な動きをしても感動することはあまりないでしょう。
また無から有を作り出すのはAIには難しいです。
人間ならではの完成が必要になる仕事は、将来も生き残り続ける可能性が高いです。
将来なくならない仕事:教育・コンサル関係
小学校教師や中学校教師といった教育関係の仕事も残り続ける可能性が高いです。
小学校や中学校の先生は、学校の勉強を教えるだけでなく、人間関係や道徳なども教える必要があります。そういった人間の機微のようなものはAIが教えるにはハードルが高いです。
またコンサルタントのような相手の悩みを聞きながら問題を解決していくような仕事もAIが奪ってしまう可能性は低いです。
パターン化された業務が少ない仕事は、将来もなくならない可能性が高いでしょう。
これから将来なくなる仕事・職業
では、これからなくなってしまう職業や仕事にはどういったものがあるでしょうか。
これからなくなる仕事・職業ランキング
これからなくなると予想される仕事には以下のようなものがあります。
- 1位:電車運転士
- 1位:経理事務員
- 3位:包装作業員
- 4位:路線バス運転手
- 4位:塵芥収集作業員
- 6位:郵便外務員
- 6位:学校事務員
- 6位:ビル清掃員
- 9位:銀行窓口係
- 9位:計器組立工
- 9位:金属製品検査工
- 12位:給食調理人
- 13位:スーパー店員
- 13位:弁当・総菜類造工
- 15位:新聞配達員
- 16位:マンション管理人
- 17位:通関士
- 18位:ホテル客係
- 19位:自動車組立工
- 20位:警備員
- 21位:測量士
- 22位:タクシー運転手
- 23位:刑務官
- 24位:秘書
- 25位:航空管制官
- 26位:プログラマー
- 27位:税務職員
- 28位:行政書士
- 29位:税理士
- 30位:航空自衛官
- 31位:弁理士
- 32位:機械修理工
- 33位:クリーニング師
- 34位:自動車板金工
- 35位:原子力技術者
- 36位:型枠大工
- 37位:公認会計士
- 38位:不動産鑑定士
- 39位:家政婦
- 40位:稲作農業者
- 41位:ラーメン調理人
- 42位:鍛造技術者
- 43位:社会保険労務士
- 44位:OA機器販売員
- 45位:司法書士
- 46位:国際公務員
- 47位:臨床検査技師
- 48位:信用金庫渉外係
- 49位:テレフォンアポインター
- 50位:大工
10年後になくなる仕事ランキング
10年後なくなる仕事
- 一般事務
- 銀行員
- 警備員
- 建築作業員
- スーパー・コンビニの店員
決められた作業を行う職種は10年後になくなってしまう可能性が高いです。
たとえば、スーパーやコンビニ店員のレジ打ち業務などもキャッシュレス化によって将来はなくなるでしょう。
また決まったルーチンを繰り返す一般事務や警備員といった職業もなくなってしまう可能性が高いです。
10年後、今以上にAIが発展すると銀行員や建築作業員など、現在のAIでは対処しきれないような範囲にもAIが広がっていく可能性は十分にあります。
AIに取って代わられる仕事ランキング
将来AIに取って代われる可能性が高い職種は以下の通りです。
AIに取って代わられる仕事
- 受付係
- 配達員
- タクシー・バスドライバー
- 工場作業員
AIはこれまでに蓄えられたビッグデータの中から必要な情報を瞬時に取り出すことができます。そのため、人間が探すよりも効率的に見つけられるため、受付係などはなくなる可能性が高いです。
また自動運転技術も進んでいるため、タクシードライバーやバスドライバーといった仕事が必要なくなる可能性があります。
このままドローン配送が進めば、配達員などの仕事も不要になります。
将来・未来になくなる職業ランキング
経済産業研究所の資料の「AIが日本の雇用に与える影響の将来予測と政策提言」によると、今後3~5年の近い将来に以下の職種がなくなるだろうと予測されています。
近い将来なくなる職業
- 一般事務・受付・秘書
- 総務・人事・経理
- 製造・生産工程・管理
一般事務や受付は、現在のAIのレベルでも一部の作業が代わりに行われています。
このままAIのレベルが上がっていけば、近い将来になくなる可能性は高いです。
ココがポイント
経理や総務といった仕事は、人間が関与する部分もあるため、完全になくなる可能性は低いですが、求人数は大幅に減少するでしょう。
三十年後になくなる仕事ランキング
30年後にはさらにAIが進化するため、かなりの職業が人間から取って代わられる可能性が高いです。
30年後なくなる仕事
- プログラマー・エンジニア
- 保険の営業員
- 卸売業者・物流業者
プログラマーやエンジニアは完全になくなるのではなく、コードを書くのが中心の下流工程の仕事がAIに取って代わられる可能性が高いです。
企画や提案などの発想力が必要な部分は30年後もまだ人間が担っているでしょう。
AIが進み、個々人の健康管理をすべて把握するようになると、保険の相談員よりもAIのほうがぴったりの商品を選んでくれるようになります。
卸売業者や物流業者も今まで工場で作っていたものが、3Dプリンターで簡単に作れるようになると不要になってしまいます。
ココに注意
10年後はまだ安心でも30年後にはなくなってしまう仕事もいろいろあります。
10年後に消える職業・仕事がある理由
現在ある仕事が10年後もそのままあるとは限りません。
10年後にその仕事がなくなってしまうのには、さまざまな理由があります。
- 技術の進歩
- 需要の減少
- 担い手がいない
仕事が10年後に消える理由①技術の進歩
10年後に仕事が消える理由として、まず挙げられるのが技術の進歩です。
近年はとくにAIの進歩がめざましく、多くの仕事がAIに取って代われるといわれています。決まった作業を繰り返すような仕事はほとんどがAIがこなすようになるでしょう。
AIによってどんどん自動化が進んでいくと、人間が担う部分が少なくなってしまいます。
仕事が10年後に消える理由②需要の減少
仕事は需要があって初めて成立するものです。
誰にも需要がないものは仕事としてやっていけません。
たとえば、昔は文字を入力してくれるタイピストという仕事がありました。しかし、今では多くの人が自分で文字をタイピングできるようになったため、なくなってしまいました。
需要があるところに供給するのが仕事の基本のため、需要がなくなれば、その仕事もなくなってしまいます。
これまではプロに相談していたようなことも、AIが代わりに答えてくれるようになれば、人間がやるべき仕事はどんどんなくなってしまうでしょう。
仕事が10年後に消える理由③担い手がいない
技術の進歩や需要の変化とは異なり、仕事を残そうと思っていても担い手がいないというケースもあります。
たとえば伝統工芸などは、どんどん次世代の働き手が減ってきており、すでになくなってしまったものもあります。
農業なども後継者がいなく、辞めてしまった人も多いです。
たとえ需要があったとしても、やる人がいなければその仕事はなくなってしまいます。
このような理由から消えてしまう仕事もあります。
将来なくならない需要がある仕事とは
これから仕事を探す場合、10年後20年後であっても残っている仕事を選ぶべきでしょう。
では将来なくならない仕事というのは、どういった特徴があるのでしょうか。
- 発想力を求められる
- コミュニケーションが重要
- 臨機応変な対応が必要
- 創造性が求められる
発想力を求められる仕事は将来もなくならない
発想力や芸術性を求められる仕事はAIに取って代わられる可能性が低いため、残り続ける可能性が高いです。
音楽や絵画といった芸術の分野でもAIプログラムは、すでに存在しています。
しかしAIが作りだした作品は、過去の作品からの学習の結果で、それを見て人間が感動することはあまりありません。
人の心を動かしたり、インパクトを与えるようなクリエイターの仕事は、10年後20年後でも残っている可能性が高いといえるでしょう。
コミュニケーションが重要な職業は今後も需要がある
人と人とのコミュニケーションが重要な仕事も10年後20年後になくなることはないでしょう。
相手の反応を見ながら対応する必要があるため、細かい気配りや相手への配慮が重要になります。
言葉や行動の裏にある感情を読み取る必要があるため、表面だけで判断するAIには、なかなか難しいです。
またサービスを受けるほうとしても、機械にやってもらうよりも人間にやってもらったほうがうれしいという理由もあります。
臨機応変な対応が必要な仕事はAIに取って代わられない
さまざまな突発的な事態が起こるような仕事もAIは苦手です。
また複数分野にわたる知識が必要だったり、経験に基づいた判断が必要な仕事も、しばらくなくなることはないでしょう。
AIは決まったことに対しては合理的な反応ができますが、イレギュラーな事態には弱いです。
たとえば医療現場や保育現場のような、常に何が起こるかわからないような場所では、人間のほうがスムーズに対応できることが多いです。
ココがポイント
医療や保育の場では、コミュニケーション能力も必要なため、まだまだAIに取って代わられることはないでしょう。
創造性が求められる仕事は10年後もAIに奪われない
創造性が必要な仕事もAIにとって変わられる可能性は低いです。
AIやロボットは情報を収集したり、検索したりといったことは得意です。
では、その情報をどのように使うのか、どう活かすのかを考えるのは人間の仕事です。
アイデアを生み出す企画職や理論を構築する研究者はAIに取って代わられる可能性は低いでしょう。
人間に役立つような道具や発送は、人間にしか産み出すことはできません。
さまざまな問題意識から、それを改善するような考えを見つけるの仕事は今後も人間が担っていくでしょう。
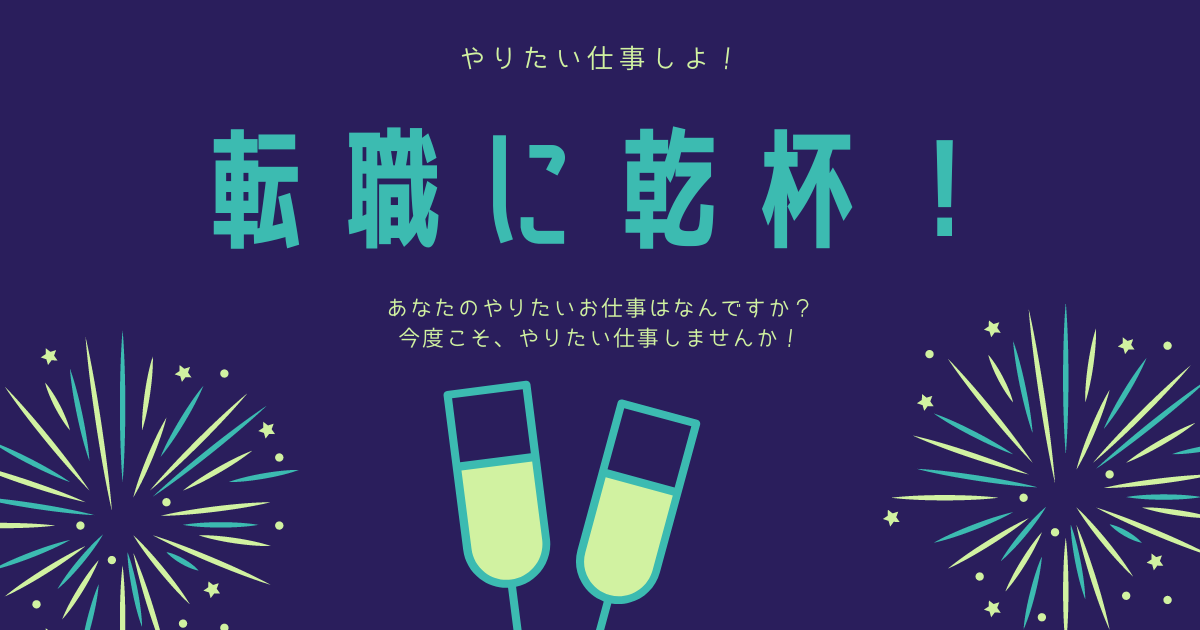
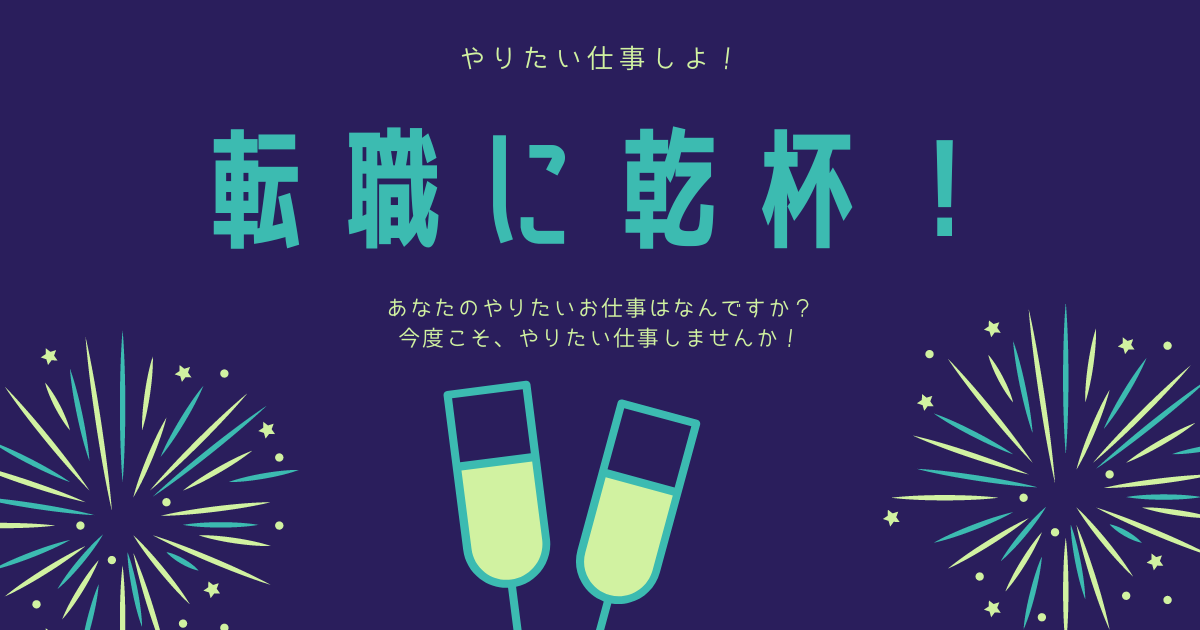
20年後はAI(人工知能)によって多くの仕事がなくなる
オックスフォード大学と野村證券が日本における601種類の職業がAIやロボットに代替される確率を試算したところ、今後10~20年で日本の労働人口の49%がAIに取って代わられるという結果がでました。
つまり約半数がAIによって代替されてしまうわけです。
もちろんこれは仮説に過ぎませんが、たくさんの仕事がAIに取って代わられることは、ほぼ確実でしょう。
AI(人工知能)の発達で格差が広がる恐れも
AI(人工知能)によって経済は拡大するものの、それによって格差も拡大するという説もあります。
資産がある人はAIを用いてどんどん事業が拡大できますが、資本がない人は単純労働を提供するしかなくなってしまいます。
そうすると、どんどん経済格差が広がってしまいます。
また失業者が増えて、年収が半減するといった可能性も指摘されています。
参照:来るべきAIによる大変化は「経済は拡大するが格差も拡大」第一人者トロント大学経営大学院教授
多くの会社員がAI(人工知能)の普及で失業者が増えると予想
転職サービスのエンジャパンの調査によると、会社員の50%がAI(人工知能)の普及で失業者が増えると予想しています。
また自分の仕事がAIに奪われるかもしれないと考えている人は17%ほどいます。
AIに仕事が奪われないと回答している人は、「仕事を作る立場」「判断が必要な仕事」「対人間の仕事」だから、自分の仕事が残り続けると考えているようです。
参考:「今後の仕事への不安(AIに代替される仕事)」について
10年後に仕事をなくさないポイント
10年後も働き続けるためには、どういったことに気をつけていけばいいのでしょうか。
将来仕事をなくさないためにも、これからのことをよく見据えていく必要があります。
- 常にアンテナを張っておく
- AIが苦手なスキルを伸ばす
- 将来残りそうな仕事・職業に転職する
将来仕事をなくさないポイント①常にアンテナを張っておく
将来仕事をなくさないためにも、しっかりアンテナを張ってトレンドを理解する必要があります。
AIやロボットには何ができて、何ができないかを把握しておくことで、AIに奪われない仕事を見つけることができるでしょう。
今後の需要などを把握しておけば、もし今の仕事を失ったとしても、これから探すべき仕事が見つかるはずです。
ただ漫然と過ごすのではなく、時代の流れを見ながらトレンドを理解することが大切です。
何かあったときには素早く対応して、新しい社会に適応していきましょう。
将来仕事をなくさないポイント②AIが苦手なスキルを伸ばす
これから将来AIがさまざまな仕事に取って代わることは間違いありません。
しかし、すべての仕事がなくなるわけではないです。
AIにも苦手なジャンルがあるため、そういったスキルを身につけることで将来も仕事を失うことなく、働き続けることができます。
たとえばAIが苦手な対人間のコミュニケーション能力を身につけておけば、10年後の仕事に困ることもないでしょう。
ココがおすすめ
想像力や発想力が身につく仕事をしておけばAIに取って代わられる心配もありません。
将来仕事をなくさないポイント③将来残りそうな仕事・職業に転職する
まだ仕事があるうちに、将来AIに取って代わられなそうな仕事に転職してしまうという手もあります。
たとえば、この記事で紹介しているような将来も残りそうな仕事に就いてしまえばとりあえずの心配はなくなるでしょう。
安心して仕事をしながら、さらにスキルアップしていくことも可能です。
新たな技術やスキルを身につけておけば、さらに別の仕事についたときでも安心して働いていけます。
変化が激しいこれからの社会を生き残るために
これからの社会は変化が激しく、数年後にも今とは環境が激変している可能性もあります。
そうした予測が難しい社会を生き残るためには以下のような努力が必要になってきます。
将来を生き抜くために①働きながら学び続ける
予測不能な将来で生き延びるためには、就職してからも学び続けることが大切です。
自分が勤めている企業や業界に関する動向はもちろん、それ以外の業界についてもアンテナを張っておきましょう。
技術は日々進化していますし、価値観もどんどん変わっていきます。
そうした時代の変化に取り残されないためにも常に学び続けることが大切です。
今は大丈夫と思われている仕事でも、数年すれば「なくなるかもしれない仕事」に変わっている可能性もあります。
ココがポイント
そうした情報を取りこぼさないためにも、さまざまな方面にアンテナを張っておきましょう。
将来を生き抜くために②柔軟に対応する
将来さまざまな変化が訪れることは、まず間違いありません。
そうした変化に対して、いかに柔軟に対応していくかが大切です。
柔軟性がないと、大きな変化に対してついていけません。
このままだと自分の仕事がなくなってしまうのだと危機感を感じるならば、何かしらアクションを起こしていく必要があります。
将来を生き抜くために③コミュニケーション能力を磨く
AIはこれからもどんどん進歩していきます。
そのため、AIが得意なジャンルで対抗しようとしても勝てない可能性が高くなってきます。
それならば人間のほうが圧倒的に得意なコミュニケーション能力を伸ばしたほうがいいでしょう。
将来生き残る仕事として、対人間とのコミュニケーションが必要なものは多くあります。
人間が得意とするコミュニケーションを伸ばすことで、将来もAIに仕事を奪われることなく、働き続けることができます。
将来のIT人材不足に備える
これからどんどんAIが導入されていくのは間違いありません。
しかし、そのための人材が整っていないのが日本の現実です。
中国やアメリカ、ヨーロッパ諸国に比べても日本のIT人材(AI人材)は不足しています。
AI関連のシステム開発に携わるAI人材が不足することが考えられるため、それに向けて備えるのも生き残る方法のひとつです。
総務省の報告によると、AI需要の伸びが平均成長率16.1%としたとき、2030年には最大12.4万人の需給ギャップが生まれると予測されています。
生き残るためにプログラミングスクールに通う
IT人材が不足しており、政府も企業もエンジニアを求めています。
そのため、プログラミングスクールに通い、エンジニアとしてのスキルを身につけるのも将来を考えると、とても有効です。
昨今はさまざまなプログラミングスクールが登場しており、自分のタイプに合ったプログラミングスクールが選べるようになっています。
おすすめのプログラミングスクール
現在未経験であっても、これからプログラミングスクールに通えば、十分にスキルを身につけることが可能です。
DMM WEBCAMP(ウェブキャンプ)


最短12週間でITエンジニアになれるプログラミングスクールです。
転職成功率98%を誇り、転職できなければ全額返金が受けられます。
未経験から即戦力を目指せる実践的な独自カリキュラムで、転職活動を有利に進められます。
デイトラ


業界最安級のWEBスキル特化型オンラインスクールです。
実務力が身につくカリキュラムで、仕事につながるWEBスキルを身につけることができます。
実際に使っている講座動画を無料で公開しているため、まずはどんな内容なのか確認してみましょう。
TECH CAMP(テックキャンプ)
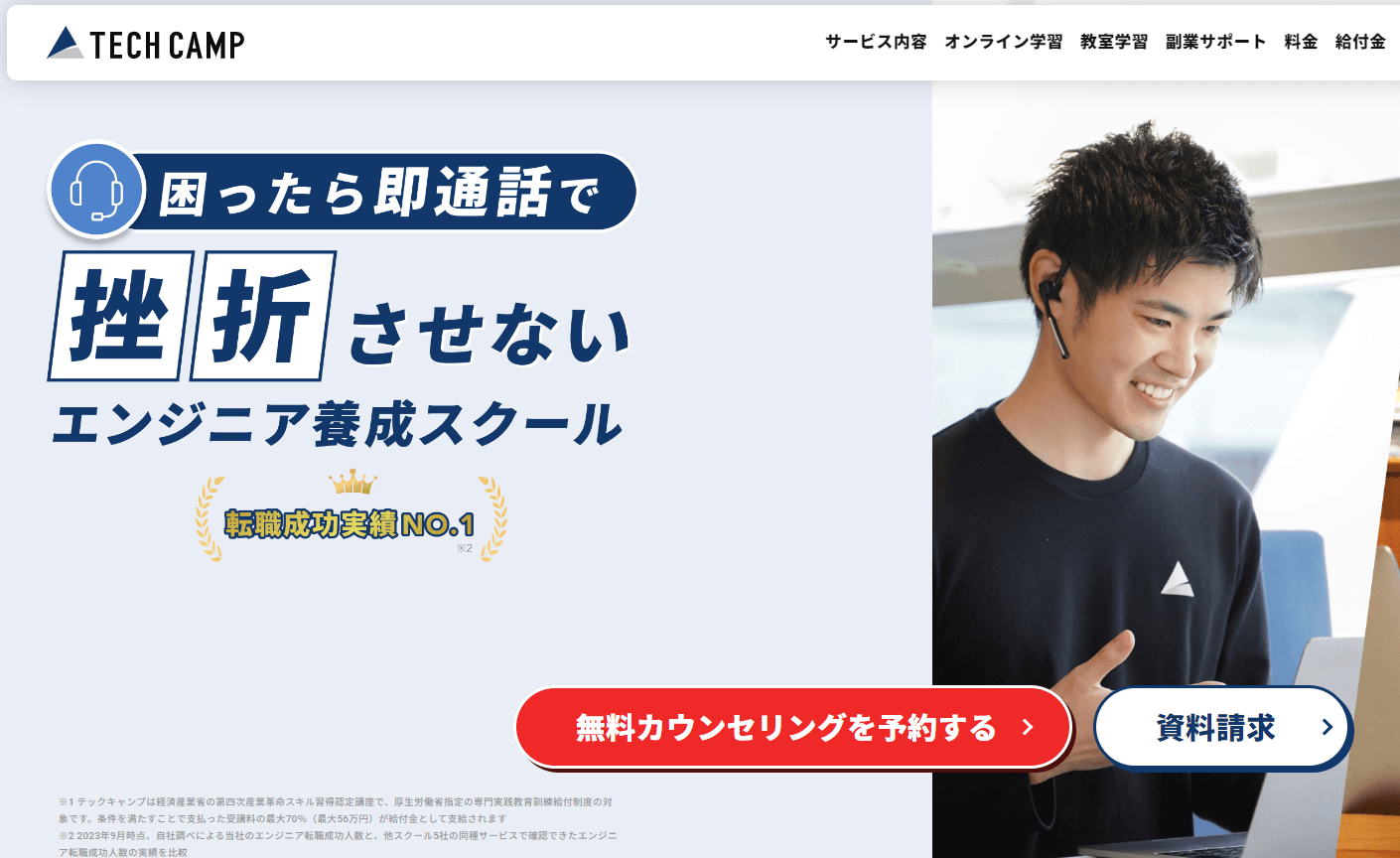
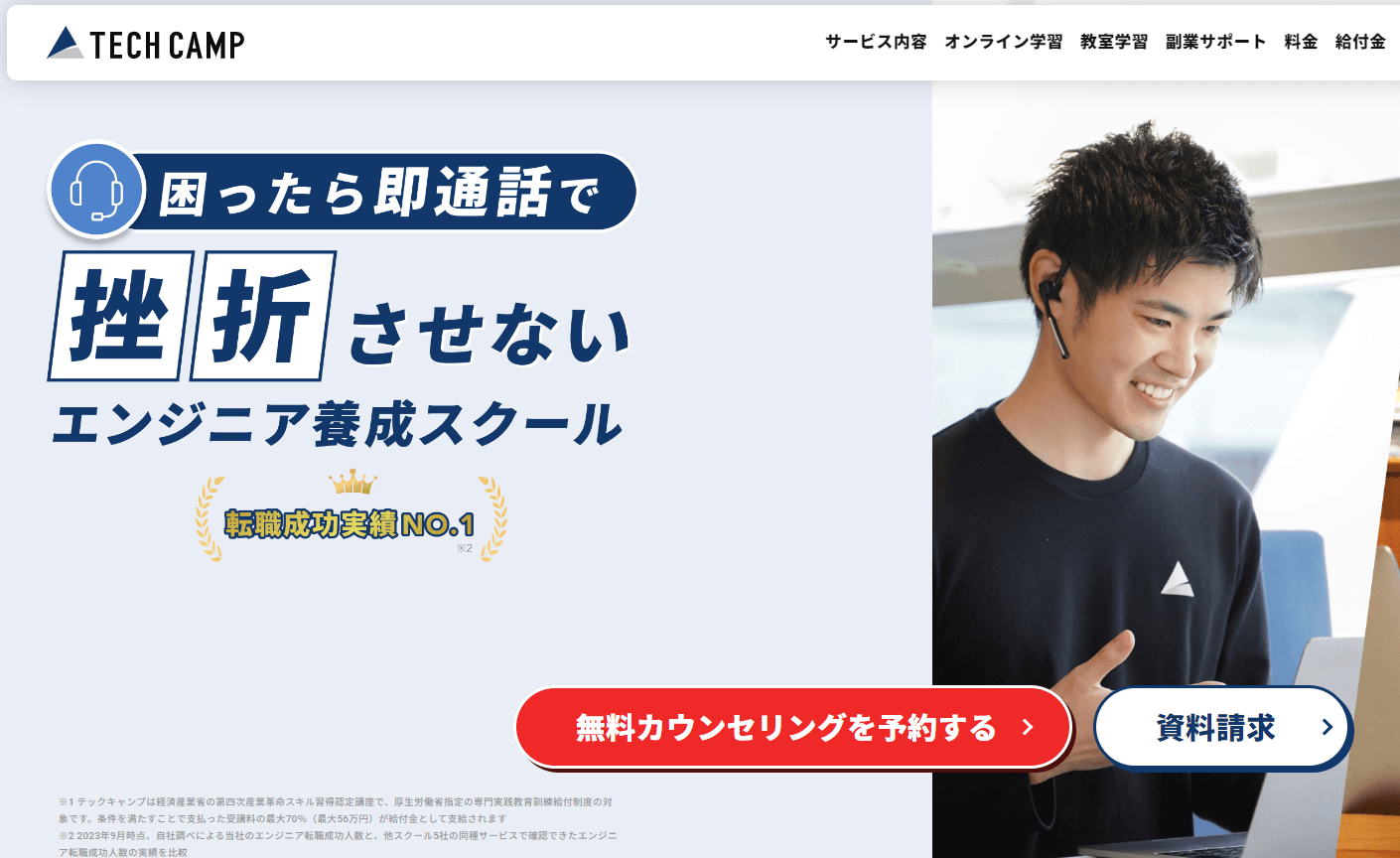
ITエンジニアに転職した卒業生の多くがリターンを実感している日本最大級のプログラミングスクールです。
転職後1~3年で、平均年収が144万円アップしており、ITエンジニアになってよかったという人が98%もいます。
未経験者に特化した学習環境が整っており、受講した人の97%がプログラミング未経験者というデータもあります。
まとめ
将来生き残る仕事となくなる仕事についてまとめました。
将来なくなりそうな仕事を見ていくと、どういった仕事がAIに取って代わられるのか想像もしやすいです。このままだと自分の仕事がなくなってしまいそうだと感じたなら、将来の仕事に向けて、いろいろと動き出しましょう。
創造力やコミュニケーション能力といったAIが苦手なところを伸ばし、10年後20年後にも問題なく働けるように準備しておきましょう。
今回の消える職業・仕事50にランクインしている人は、今一度将来についてよく考え直してみてください。
コメント