- 一度旦那の扶養から抜けてまた入ることはできる?
- パートの扶養の範囲はいくらまで大丈夫?
- 夫の扶養から外れるとき手続きはどこですればいい?




扶養に入るためにはいくつかの要件があります。
その要件を満たしていないと扶養から抜ける必要があります。
ただ、一度扶養から抜けても、また要件を満たせば扶養に入ることは可能です。
この記事では扶養から外れることのメリット・デメリットや扶養から外れてまた扶養に入るときの手続きについてまとめています。
一度扶養から外れると戻れないは嘘!また扶養に入れる
一度扶養を外れたとしても、扶養に入るための要件を満たし、手続きをすれば再び扶養に入ることができます。
ただし一言で「扶養」といっても税制上の扶養と社会保険の扶養の2種類があり、それぞれ入る条件や外れる条件が異なります。
税制上の扶養:配偶者控除・配偶者特別控除について
配偶者控除(配偶者特別控除)とは、配偶者の所得が一定以下ならば、世帯主の所得税や住民税が安くなるという制度です。
この税制上の扶養は、配偶者の1年間の年間所得によって決まります。
もし配偶者の所得が基準を超えると、扶養から外れます。
しかし、その翌年の所得が基準内であれば、再び扶養に戻ることができます。
社会保険の扶養:見込み年収130万円未満で戻れる
夫の社会保険の扶養に入ると、妻の社会保険料の負担はなくなります。
つまり社会保険(公的年金・健康保険・介護保険)がすべて無料になります。
社会保険の扶養に入るためには、見込み年収130万円未満という条件を満たさなければなりません。
見込み年収130万円を超えてしまうと扶養から外れます。
税制上の扶養では1~12月という期間の区切りがありましたが、社会保険ではそういった区切りはありません。
ココがポイント
過去の収入は関係なく、現在の収入から見込まれる見込み年収130万円未満と認められれば扶養に戻ることができます。
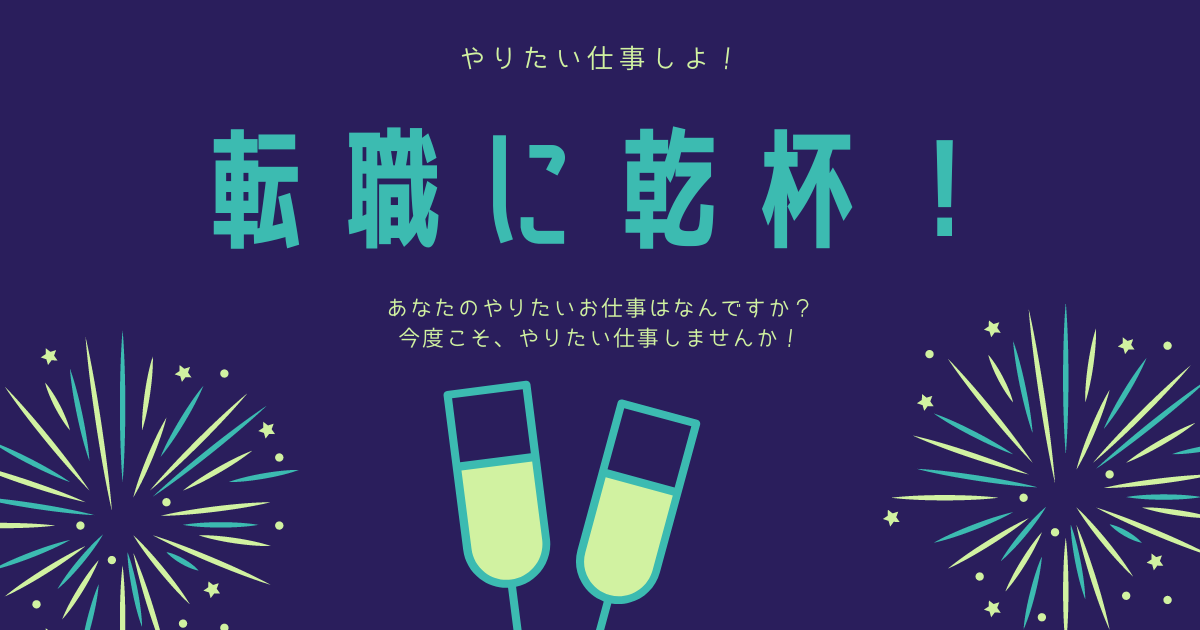
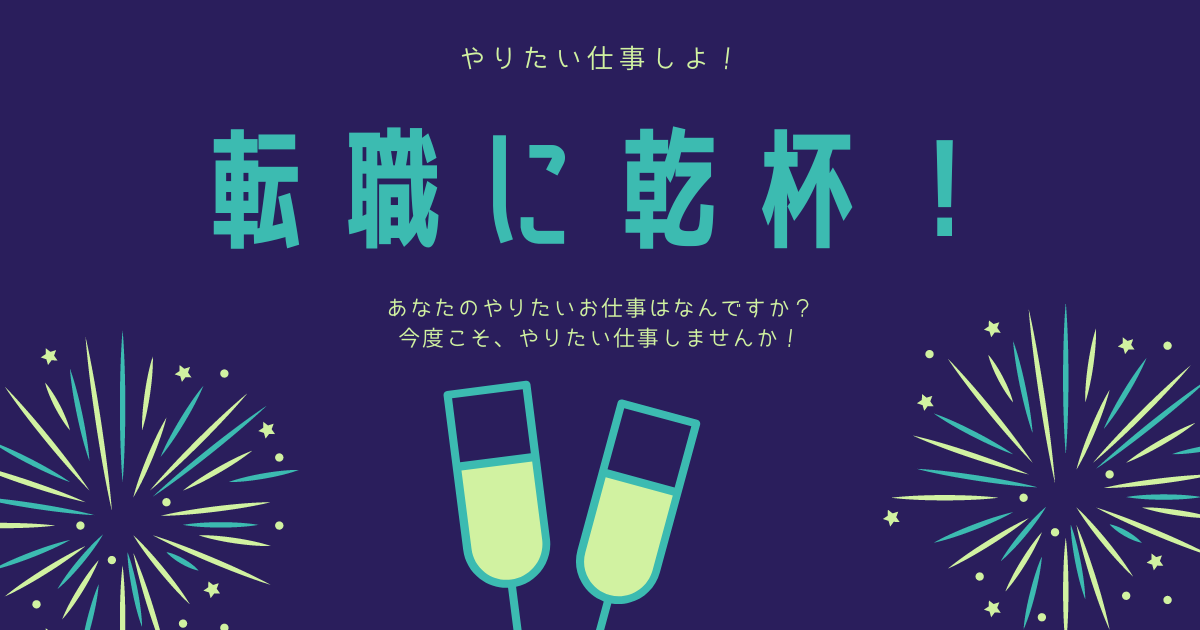
扶養から外れるタイミング
これまで扶養される立場だった人が、扶養から外れるのはどんなタイミングなのでしょうか。
こちらも税制上の扶養と社会保険の扶養でタイミングが異なります。
税制上の扶養から外れるタイミング
税法上の扶養は、給与収入が150万円を超えると、配偶者特別控除を満額利用することができなくなるため、扶養から外れてしまいます。
2018年の配偶者特別控除の見直しによって、夫が配偶者特別控除を利用する場合の妻の年収は103万円から150万円に変更されました。
ただし所得税の課税対象になるかどうかは103万円が基準になっているため「103万円の壁」はまだ存在しています。
社会保険の扶養から外れるタイミング
給与収入が130万円を超えると社会保険上の扶養から外れます。
給与収入130万円を超える場合と規定されていますが、目安としては月額の給与が108,333円を越えている場合は、扶養から外れる手続きを行ったほうがいいです。
扶養から外れる際に必要な手続き
扶養から外れる場合には、手続きが必要になります。
状況によって手続きが変わってくるため注意しましょう。
配偶者特別控除から外れるとき
妻の年収が201万円(合計所得133万円)を超えると、配偶者特別控除の対象から外れます。
このとき、夫は年末調整または確定申告するときに申請手続きをすることになります。
この場合、今まで申請していた配偶者控除を適用せずに提出するだけでOKです。
たとえば年の途中で配偶者控除から外れそうだとわかったならば、年末調整の申告書を提出するときに厳選控除対象配偶者の欄を空欄にしておきましょう。
年末調整で一緒に提出する配偶者控除等申告書については、項目に記入していても合計所得が133万円を超えていれば控除の対象にはなりません。
社会保険の扶養から外れるとき
妻が勤務先の社会保険に加入することで扶養から外れることがわかった場合、届出を提出する必要があります。
この場合、夫が会社の担当事務に伝えて被扶養者異動届に記入することになります。
社会保険の扶養から外れた場合、妻は自身の保険料を毎月自分で支払うことになります。
もし国民健康保険に加入した場合は、送付される納付書を使って支払うことになります。
一度扶養から外れてまた扶養に入る手続き
一度扶養から外れてまた扶養に入る場合、どういった手続きが必要になるのでしょうか。
税制上の扶養は年末調整・確定申告で申請
配偶者控除や配偶者特別控除といった税制上の扶養を受けるためには、会社の年末調整のタイミングで申請します。
年末調整の際、給与所得者の配偶者控除等申告者を作成して、提出すればOKです。
税制上の扶養に再び入る場合、年の途中で手続きする必要がありません。
年末調整の際に、配偶者の合計所得金額(1~12月)次第で控除が受けられるかどうかわかります。
ココに注意
社会保険の扶養は夫の会社に申請
社会保険の扶養に入ったり、外れたりするための手続きは、夫の会社の社会保険担当を通じて手続きします。
会社の健康保険組合によって必要になる書類が異なります。どの書類が必要になるのか確認しておきましょう。
基本的には扶養認定は1ヶ月以上さかのぼらないため、扶養に戻れる状態になったならば、できるだけすぐに手続きするようにしましょう。
扶養に戻るためには見込み年収130万円未満を証明する書類が必要になります。
国民年金の手続き
たとえば妻が個人事業主をやっていて、売上が低下して扶養に戻りたい場合、国民年金のためにすべき手続きはとくにありません。
夫の会社に「扶養に戻りたい」と伝えれば、会社から必要な書類の提出を求められるため、それに従って書類を提出しましょう。
そうすれば会社と役所で話を進めてくれるため、自分ですべき手続きはありません。
ココがポイント
もし国民年金を前納している場合は、過剰に支払った分が還付されます。
国民健康保険の手続き
国民健康保険を停止するためには役所の窓口での手続きが必要になります。
まず夫の会社の健康保険に加入させてもらい、健康保険証を発行してもらいます。
その後、会社の健康保険証と今まで使っていた国民健康保険の保険証を役所の窓口に提出すれば変更手続きができます。
扶養から外れるメリット
扶養から外れると以下のようなメリットがあります。
- 扶養されていた人が自由に働ける
- 社会保険の保障が手厚くなる
扶養から外れるメリット①扶養されていた人が自由に働ける
今まで扶養されていた人が扶養から外れると、給与のことを気にせずに自由に働けるようになります。
扶養に入っている間はどのくらいまで稼いで大丈夫なのか、いちいち計算していた人も多いはずです。
扶養から外れれば年収を抑える必要がないため、シフトを増やしたり、条件がいい勤務先に移ったりできます。
もちろんフルタイムの正社員として働くことも可能です。
ココがポイント
社会の中で活躍したいならば、扶養から外れたほうが自由に動けます。
扶養から外れるメリット②社会保険の保障が手厚くなる
扶養から外れると今まで扶養に入っていた人の社会保険の保障が手厚くなり、老後の年金が増える可能性があります。
扶養されている場合、社会保険の負担はありませんが、老後に受け取れる年金は国民年金だけです。
扶養から外れると自分で社会保険料を支払うことになりますが、厚生年金に入れば国民年金よりも保障が手厚くなります。
老後にもらえるお金が増えるため、ゆとりのある老後生活が送れるようになります。
扶養から外れるデメリット
扶養から外れると以下のようなデメリットがあります。
- 住民税・所得税を支払わなければならない
- 扶養していた人の節税効果がなくなる
- 社会保険料を支払わなければならない
扶養から外れるデメリット①住民税・所得税を支払わなければならない
扶養から外れると、これまで負担していなかった住民税や所得税を納める義務が発生します。
税制上の扶養に入っていれば、住民税や所得税は納める必要がありません。
しかし収入が増えて税制上の扶養から外れてしまうと、これまで扶養されていた人に納税義務が発生します。
扶養から外れるデメリット②扶養していた人の節税効果がなくなる
これまでに扶養していた人の節税効果がなくなってしまうのもデメリットのひとつです。
配偶者の所得が扶養内だと配偶者控除が適用され、配偶者が納めるべき所得税や住民税が減額されます。
しかし扶養から外れると、そういった節税効果がなくなってしまいます。
扶養から外れるデメリット③社会保険料を支払わなければならない
扶養から外れると、社会保険料を負担する義務が生じます。
社会保険上の扶養に入っていれば、扶養者の社会保険が適用されたため、国民年金保険を支払う必要がありませんでした。
しかし扶養から外れると、自分で年金保険や健康保険を支払わなければなりません。
扶養から外れることによって出費が増えてしまうのが大きなデメリットといえるでしょう。
扶養を外れていることがバレたらどうなる?
仕事を掛け持ちした結果、年収が増えてしまい扶養の範囲を越してしまうことがあります。
扶養を外れているにもかかわらず、扶養に入ったままにしておくとどうなるのでしょうか。
妻の扶養に対して税務署から書類が届く
夫が勤めている会社に対して年末調整で「妻を扶養しています」と申告すると、その分控除で税金が安くなります。
しかし、妻の収入が不要の範囲を超えていると、夫の申告は事実ではなくなってしまいます。
そうすると税務署から夫が勤めている会社宛に「扶養控除等の見直しについて」と記載された通知が届きます。
会社の従業員から妻を扶養していると申告がありましたが、誤りではないですかという内容です。
誤りではないですかと質問する形式を取っていますが、これを送付している時点で税務署は事実を確認していることがほとんどです。
ココがポイント
税務署では最大3年までさかのぼって扶養についての確認を行います。
扶養についての確認がなされ結果によっては追加納税を
通知が届くと会社から従業員に対して事実の確認が行われます。
確認方法は会社によって異なりますが、最大3年分にさかのぼって妻の所得証明・確定申告書・給与明細などのコピー提出を求められることが多いです。
そうして再計算を行い、本来納めるべき税金より、実際に納めている税金が少ないとわかれば不足分をまとめて納税することになります。
給与から差し引くなどして会社にお金を払い、会社が税務署に対して納税します。
会社として、多少の手間はかかりますが、何度も同じようなことがない限り、単純に処理して終わりになります。勤めていく上で大きく問題になるようなことはありません。
妻と夫で意思の疎通をすることが大切
妻が働いてどれくらいの収入を得ているかはしっかり夫に話しておくべきです。
最初から扶養に入っていないならば、とくに問題はありませんが、扶養に入っている場合、収入によっては扶養から外れる手続きが必要なため、両者の意思の疎通が大切です。
不要で申告している夫も年末調整で修正が必要になるため、さまざまな手続きをやり直す必要が出てきます。
扶養関係がある場合、その都度状況を確認しなければなりません。
ココがポイント
外部から指摘されて問題になる前に、夫婦間でしっかり確認を取っておきましょう。
妻が扶養から外れると夫の税金はどのくらい増える?
妻が夫の扶養から外れると、どのくらいのお金がかかるようになるのでしょうか。
扶養から外れると夫の税金は約2万円以上増える
妻が雇用から外れると配偶者控除が使えなくなるため、夫の支払う税金の増えます。
| 課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
配偶者控除が完全に使えなくなると、課税所得金額が38万円増えます。
夫の課税所得金額を確認して、それに対応した税率に38万円をかければ、夫の税金がいくら増えるのか求められます。
夫の課税所得金額がもっとも少ない場合でも19,000円は増えることになります。
配偶者控除について
妻がパートで働いていて、年収が103万円以下ならば配偶者控除が適用されます。
この条件に合致すれば38万円まで配偶者控除を受けることが可能です。
ただし38万円は最大値で、夫の合計所得金額によって控除額が変わってきます。
もし夫の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除は受けられなくなります。
| 夫の合計所得金額 | 配偶者控除額 |
| 900万円以下 | 38万円 |
| 900万円超950万円以下 | 26万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 13万円 |
配偶者特別控除について
配偶者特別控除は2018年から始まった制度です。
妻の年間の合計所得金額が48万円より多くなったときに利用できます。
配偶者特別控除の金額は条件によって細かく設定されています。
| 妻の合計所得金額 | 夫の合計所得金額 900万円以下 | 夫の合計所得金額 900万円超950万円以下 | 夫の合計所得金額 950万円超1,000万円以下 |
| 48万円超 95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
まとめ:一度扶養から外れると戻れないわけではない
たとえ一度扶養から外れてしまっても、要件さえ満たせば再び雇用に入ることは可能です。
ただし、扶養から外れる場合はしっかり諸々の手続きをしておく必要があります。手続きをしないと税務署から確認されることになるため注意しましょう。
妻の収入がどのくらいかによって扶養に入れるかどうかは変わってきます。もし積極的に働きたい場合は雇用から外しておくようにしましょう。
コメント