- パートで社会保険に加入したくないとき理由はどうする?
- パート先の社会保険入らないとどうなる?
- パートで社会保険に入るといくら引かれる?




夫や親の扶養に入っている場合、アルバイト・パートの年収や勤務時間が一定を超えてしまうと、自分のアルバイト先やパート先で健康保険や厚生年金保険に加入する必要があります。
その場合、保険料の支払いが発生します。
では、パート先の社会保険に加入しない場合はどうすればいいのでしょうか。
扶養範囲内で働くパート主婦が覚えておきたいこと
パートで働く主婦にとって、配偶者の扶養内にすることで得られる扶養控除は大きなメリットがあります。
しかし、扶養についての正しい知識を持っている人はそこまで多くないかもしれません。
扶養の範囲内とは
扶養とは、経済的な理由から自力で生活できない者の面倒を見ることを意味します。
たとえば、夫が働いて収入を得て、妻や子どもが仕事をしていない場合、妻と子どもは夫の扶養家族と定義づけられます。
では妻がパートやアルバイトなどで働くようになれば、扶養家族ではなくなるのでしょうか。
妻がパートなどで仕事をしている場合、年収によっては扶養範囲内と扱われます。
仕事をしていても扶養範囲であれば、さまざまな控除を受けることができます。
妻の所得税が免除されるほか、夫の所得税に対しても控除が適用されます。
扶養から外れるとどうなる?
では、夫の扶養から妻が外れてしまったらどうなるのでしょうか。
扶養外になると、一気に税金の負担が増えてしまうのでしょうか。
こういった急激な負担を避けるために設けられたのが、配偶者特別控除です。
これにより段階的に控除を受けられるようになったため、一気に負担が増えるようなことはなくなりました。
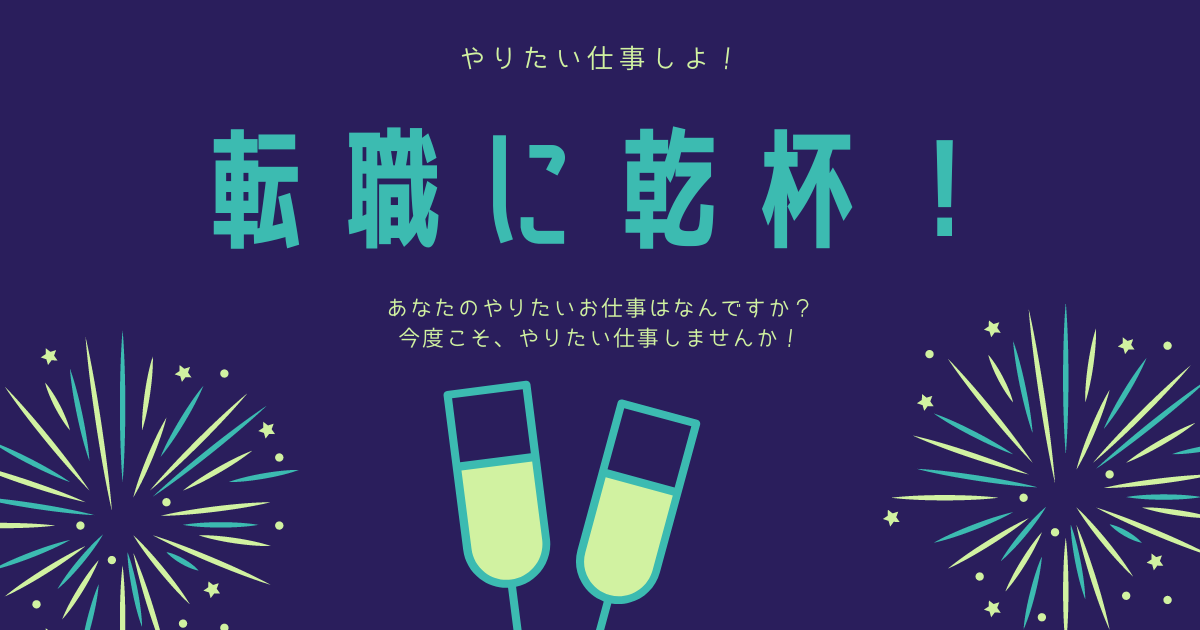
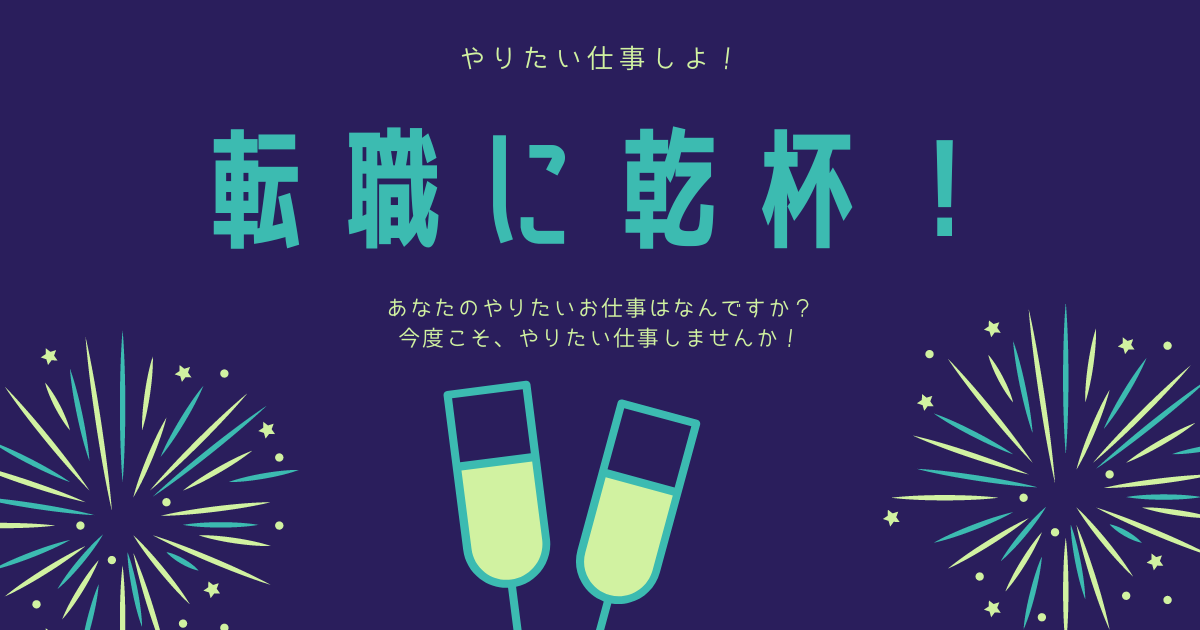
社会保険上の扶養について
夫の扶養範囲内であれば、妻は第3号被保険者となるため、社会保険料を支払う必要がありません。
扶養範囲となる上限の収入は130万円です。
また年間の給与が106万円を超えると、夫の扶養範囲を外れることがあります。これがいわゆる「106万の壁」です。
社会保険料の支払い義務が発生すると、給料から天引きされるようになるため、手取金額が少なくなってしまいます。
ココがポイント
扶養範囲内におさめるためには、月にいくらまで働くことができるのか理解しておく必要があります。
2022年10月からの社会保険加入条件の変更点
2022年10月からパートやアルバイトの社会保険の加入条件に変更が加わりました。
これにより勤務先の従業員数と雇用見込み期間の2つが変更されています。
2022年10月から変わる社会保険の扶養内①従業員数
2022年10月から社会保険の支払い義務の範囲が、従業員数501人以上から従業員数101人以上に変わりました。
さらに2024年10月からは従業員数51人以上に適用が拡大される予定です。
今までは大企業に勤めていなければ社会保険の支払い義務は発生しなかったのですが、この変更により、中小企業に勤める扶養内のパート主婦にも社会保険支払いの義務が発生するようになります。
参考:従業員数500人以下の事業主のみなさま | 厚生労働省
2022年10月から変わる社会保険の扶養内②雇用見込み期間
2022年10月から雇用見込み期間が1年以上から2ヶ月以上に変更されました。
従来は1年以上の長期パートだと社会保険加入の義務があったのですが、2022年10月からは雇用見込み2ヶ月を超える短期パートでも社会保険に加入しなければなりません。
たとえ雇用契約期間が2ヶ月以内であっても、更新によって2ヶ月以上の雇用見込みがある場合は、社会保険を支払う必要があります。
パート先の社会保険に加入しない方法【2022年10月以降】
パート先の社会保険に加入したくない場合は、年収106万円未満、月収約8.8万円未満にして、週の労働時間を20時間未満に収まるようにしなければなりません。
以下の社会保険の加入条件を満たさなければ、社会保険への加入の義務は免除されます。
社会保険の加入条件
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 賃金月額88,000円以上、年額106万円以上
- 2ヶ月を超える雇用が見込まれる
- 従業員101人以上
- 学生ではない
この要件をすべて満たすと、社会保険に入らなければなりません。
考え方を変えると、これらの要件を満たさないようにすれば社会保険に加入しなくてもいいことになります。
- 年収106万円未満にする
- 労働時間・日数を正社員の4分の3未満にする
社会保険に入りたくない人は年収106万円未満にする
社会保険に入りたくない人は、年収106万円未満に抑えるようにしましょう。
そうすると上記の「年収106万円以上」を満たさなくなるため、社会保険に入らなくて済むようになります。
月収でいうと平均8.8万円を超えていると社会保険に入らなければなりません。
労働時間・日数を正社員の4分の3未満にする
上記の5つに当てはまらなくても、正社員の4分の3以上シフトが入っていると、学生であるかどうかに限らず、勤務先の社会保険に入らなければなりません。
たとえば勤務先の正社員の1週間の所定労働時間が40時間で収入2日の会社だと、1週間の勤務を30時間未満、月16日未満にする必要があります。
ただしこの場合、労働時間および労働日数のどちらかだけが超えた場合は、社会保険に加入する必要がありません。
パート先で社会保険に加入しなくてもいい条件
社会保険に加入するのを防ぐには、年収や労働時間を調整するのがやりやすいです。
しかし、パート勤務をしている主婦は、もっと稼ぎたいと考えている人が多いでしょう。そういった場合は、自分に関係があるもので条件を満たすことで、社会保険に加入しなくてもよくなるようになります。
- 学生であること
- 2ヶ月以上の雇用見込みがないこと
社会保険に加入しなくてもいい条件①学生であること
学生であれば社会保険に加入しなくても構いません。
この場合の学生は、高校・大学・大学院をはじめ、学校教育法で規定された専修学校や各種学校に通っている人で、こういったケースでは社会保険への加入義務が免除されます。
ただし、通信教育や夜間・定時制の学校だと対象外になります。学校を休学している場合も対象外です。
社会保険に加入しなくてもいい条件②2ヶ月以上の雇用見込みがないこと
雇用期間に制限がない場合や雇用期間が2ヶ月以上となっている場合、雇用見込みありになり、社会保険加入の義務が発生します。
また雇用期間が1年未満でも、その都度契約更新の手続きを組む場合や同じ仕事で1年以上更新された実績がある場合も、雇用見込みありの扱いになります。
社会保険に加入したくない場合には、このような状況になることを避けなければなりません。
パート先の社会保険に加入したくない理由【2022年以降】
それぞれいろいろな事情があるでしょうが、ではどうしてパート先の社会保険に加入したくない人が多いのでしょうか。
社会保険に加入することで発生するデメリットには以下のようなものがあります。
- 社会保険の扶養から外れる
- 月の手取りが減る
パート先の社会保険に加入したくない理由①社会保険の扶養から外れる
パートやアルバイトで働いている人は、旦那さんなどの給与所得者の扶養に入っていることが多いです。
扶養に入るためには税制上と社会保険上のそれぞれ設けられたラインを超えないことが条件になっています。
社会保険上の扶養を受けている場合、第3号被保険者として扱われ、被扶養個人が保険料を納める必要がないほか、介護保険料なども支払う必要がありません。
パート先の社会保険に加入すると、第2号被保険者として扱われます。
そうするとさまざまな保障を受けられるようにはなりますが、手取りの中から各種の保険料が天引きされてしまいます。
パート先の社会保険に加入したくない理由②月の手取りが減る
パート先の社会保険に加入したくない主な理由は、やはり月々の手取りが減ってしまうからでしょう。
社会保険料を支払うようになると、毎月振り込まれる給与から自動で天引きされるようになります。
家計を支えようとして働いているはずなのに、給与からお金が引かれてしまえば、何のために働いているのかわからなくなってしまいます。
単純に手元に残るお金が少なくなってしまうため、パート先の社会保険に加入したくないという人が多いです。
パート先の社会保険に加入するメリット
パート先の社会保険に加入するデメリットとして、手取りが減ってしまうことが挙げられます。
ではパート先の社会保険に加入すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。
主なメリットしては以下の3つが挙げられます。
- もらえる年金が増える
- 手当金の支給対象になる
- 年収を気にせずに働ける
社会保険に加入するメリット①もらえる年金が増える
社会保険に加入すれば、厚生年金を給与所得ごとに納める必要が出てきます。
厚生年金を納めると、将来受け取れる年金の受給額が増えます。
これまでもらえる予定であった基礎年金にプラスして厚生年金ももらえるようになるため、給付が上乗せされます。
加入期間が長くなれば長くなるだけ、将来的に上乗せされる年金額の増額も見込めます。
社会保険に加入するメリット②手当金の支給対象になる
パート先の社会保険に加入すると、傷病手当金や出産手当金、出産育児一時金などの支給対象になります。
保障内容の多くは、国民健康保険の保障内容よりも充実しているため、社会保険を支払う分だけの価値は十分あります。
社会保険制度の内容
- 公的医療保険制度
- 公的年金制度
- 雇用保険制度
- 雇用保険
- 公的介護保険制度
社会保険に加入するメリット③年収を気にせずに働ける
社会保険に加入せず、扶養内で働くためにはシフトを組むときに労働日数や年収額など、さまざまな調整を行い、仕事をしています。
一度社会保険に加入してしまえば、こういったことは一切気にせず、働きたいだけ働けるようになります。
仕事に打ち込むことで、ワンランク上のキャリアを目指すことも可能です。
年収額の上限がなくなることで、給与所得者との年収を合算して住宅ローンを組んで住宅を購入することもできるようになります。
どんどん年収を増やしていけば、扶養内で働いていたときよりも世帯収入が増える可能性が高いです。
106万円の壁・130万円の壁を超えるといくら払う?
社会保険加入の条件を満たし、扶養から外れてしまうと、実際にいくら支払う必要が出てくるのでしょうか。
106万円の壁を超えた場合に支払う社会保険料
たとえば、パート従業員(賞与なし)の場合、給与の月額が88,000円だったとします。
そうすると以下のような保険料を支払うことになります。
- 健康保険料:10,076円(折半額5,038円)
- 厚生年金保険料:16,104円(折半額8,052円)
社会保険の半分は会社に負担してもらうため、実際に支払うのは折半した金額です。
そのため、合計26,180円の折半額である13,090円が月に支払うべき社会保険料となります。
130万円の壁を超えた場合に支払う社会保険料
パート従業員で給与の月額が109,000円の場合、支払う社会保険料は以下の通りになります。
- 健康保険料:12,595円(折半額6,297.5円)
- 厚生年金保険料:20,130円(折半額10,065円)
社会保険料の合計は32,725円となるため、その半分の16,362円が月々に支払うべき保険料です。
106万円の壁を超えると月額約1.3万円、年間15.7万円の社会保険料の負担が増えることになります。
130万円の壁を超えると月額約1.6万円、年間約19.6万円の社会保険料を支払うことになります。
社会保険の扶養範囲は年収130万円の壁にも注意
親や配偶者などの扶養範囲内でいるためには、年収を130万円未満に抑える必要があります。
130万円の壁は、勤務先の社会保険加入の条件ではなく、親や配偶者の扶養から外れる年収なので、こちらも覚えておく必要があります。
①130万円未満・労働時間が正社員の4分の3未満
親や夫の社会保険の扶養に入れます。
20歳以上60歳未満の人は、国民年金は自分で加入手続きをして保険料を支払う必要があります。
配偶者の勤務先の社会保険の扶養になっている場合は、国民年金第3号被保険者となり、保険料を自分で支払う必要はありません。
手続きなども勤務先が行ってくれます。
②130万円未満・労働時間が正社員の4分の3以上
社会保険加入の条件を満たすため、親や配偶者の社会保険の扶養を外れ、自分で支払う必要があります。
③130万円以上・労働時間が正社員の4分の3未満
所定労働時間が少ないため、勤務先の社会保険には加入できません。
しかし収入が130万円以上だと親や配偶者の扶養を外れるため、自分で国民健康保険と国民年金を支払う必要があります。
130万円の壁は掛け持ち年収でカウント
106万円の壁は、1つの勤務先での社会保険加入の話ですが、130万円の壁は掛け持ちしている分を含めた合計年収で判断されます。
掛け持ちしているパート代の年収が130万円以上になると扶養を外れて、社会保険料を自分で支払う必要があります。
そのため、社会保険料を支払いたくない場合は、収入の合計が130万円以上にならないよう気をつけましょう。
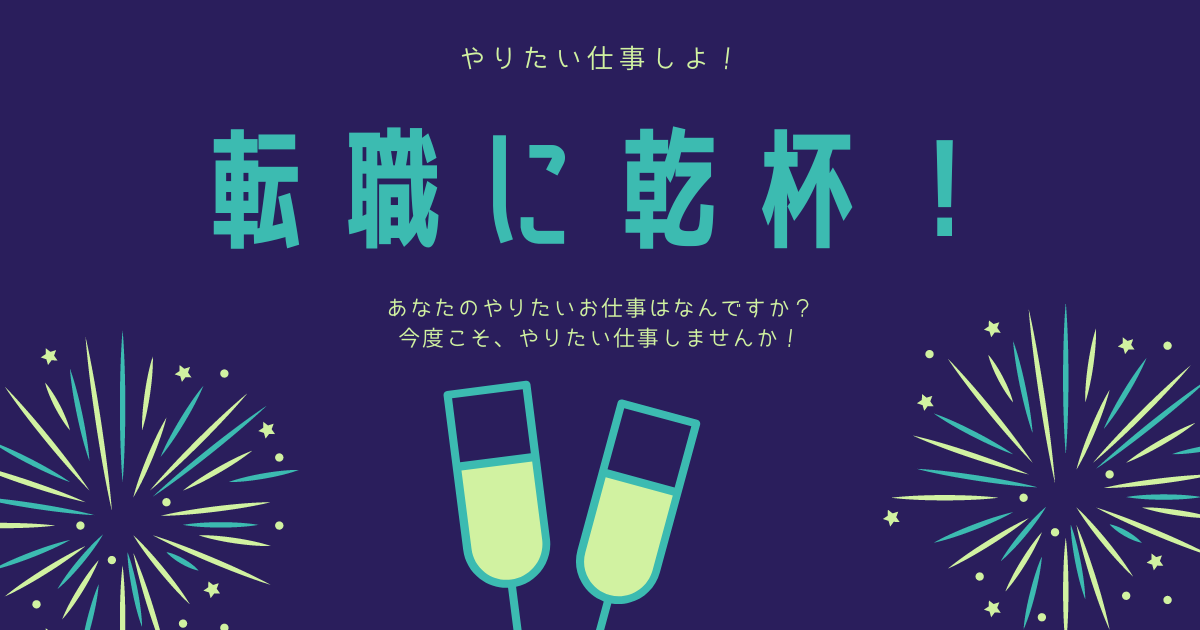
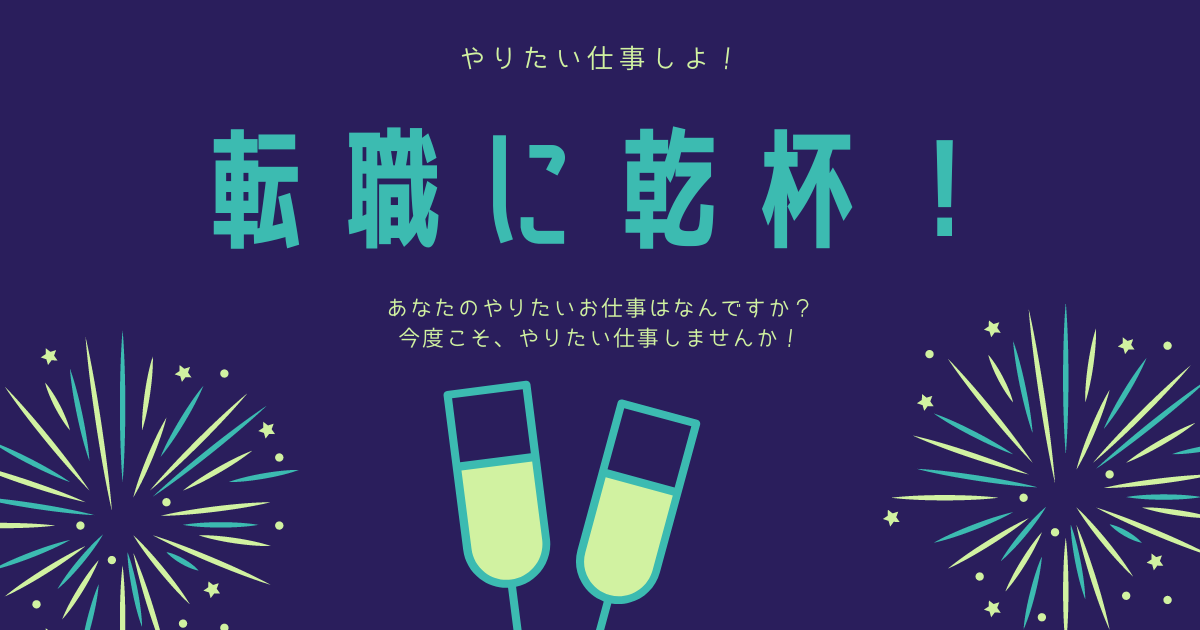
まとめ
年収が106万円以上あり、社会保険加入の要件すべてを満たすと社会保険料を自分で支払う必要があります。
給与から毎月天引きされるため、手取りの額が減ってしまいます。
もし会社の社会保険に加入したくない場合は、これまでの働き方を見直す必要があります。
パートの勤務時間を減らしたり、従業員が少ないところに転職したりして、社会保険加入の要件を満たさないようにしましょう。
2022年からの改正により、社会保険加入条件の範囲が広がっているため、どういったところが変わったのかもしっかり理解しておくことをおすすめします。
コメント